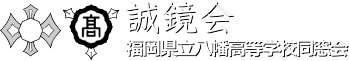<八高つれづれ草子> 第1回
上X国語翁 第1回
【 手に届く花を摘め 】
わが家の畑キュウリがスルスルっと手を伸ばし、自在に上って行きます。植物のツルの動きはほんとにミラクル。何を感じながらつかまる相手を見つけて伸びて伸ばして。

さてキュウリが手を伸ばす様を見ていてポンと浮かんできた言葉、「手に届く花を摘め」です。話しはぶっ跳びます。
この言葉には <Gather ye rosebuds while ye may > という英語の出典があります。直訳は「あなたにとって適当な時期に、バラを摘みなさい」くらいかな。辞書には「若いうちに青春の幸福を味わえ」という訳もあります。
この言葉は、教師なりたての時期、哲学か倫理学の先生の書いた『高校生への手紙』という本で見つけたもので、そこにはこの「手に届く花を摘め」を
・・・・人生は、一隻の小さな舟に乗って、川を、上流から、中流、下流へと向かって旅するようなもの。その川岸には、その時期その場所でしか手にすることが出来ない花が咲いている。人はその時期その場所で、手を伸ばしてそれらの花を摘まなければ、生涯それを手にすることが出来ない・・・・というふうに説明していました。
僕は若い時期、あちこちの川でカヌーを浮かべてました。上流も中流も下流もそれぞれの表情で、人を近づけたり遠ざけたり、楽しくさせたり怖がらせたりです。確かにそこでなければ味わえないものがありますね。

僕はクラスや学年を持つと、この「手に届く花を摘め」を見出しに通信を書いて配ることが何度かありました。その文章の結びはたとえばこんなふうです。
・・一度きりの高校生活。手に届く花を見過ごさず、学び、経験し、大いに楽しむことだ。モチベーションをかき立てて、自分なりに人生の上流の花を見つけるといい。ここは自分が未熟なことを正面から認めながら、失敗や挫折にめげず、大いに自分を試す場所だ。若いみんなが、生きることにいい加減になったり、ぐうたらになったりしないことをひたすら望む。ぐうたらや、のんびり、ぼんやりは、人生の旅が下流にさしかかってからの楽しみに回しておけばよい。

さて、こんなことを書いていた僕自身が、今やその人生の下流の旅にさしかかっているところ。「生きることにいい加減になったり、ぐうたらや、のんびり、ぼんやり・・・」確かにそうか?ちょっと待てよ、の気分もあります。
人生ここに来て、孫が現れた。ソラマメやフキが美味しく食えるようになった。ジャガイモや落花生を自分で作れるようになった。動きが鈍くなった。自由人になった・・・。
今回「手に届く花を摘め」という言葉を思い出して、少し新鮮な気分で今の自分の様子や人生の形を眺め返しているところです。みなさんは、どのあたり、いかがなものか。
「手に届く花」に気付くこと。受け容れて喜べること。今回文章を書いた収穫です。
高校27期 上掛靖良